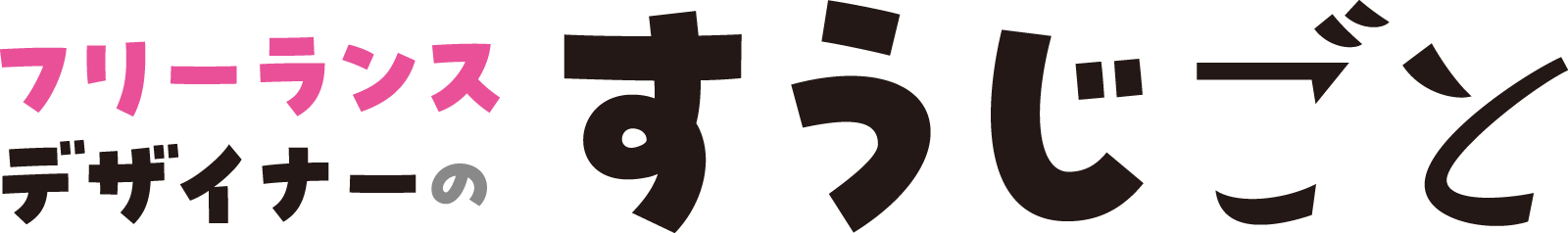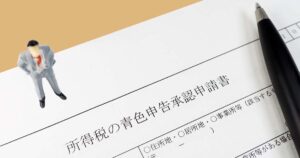インボイス制度の施行まで、あと約2ヶ月!
仕組みについては理解できましたでしょうか。
国税庁の通知って難解すぎますよね。わざと暗号みたいにしてるのかと思うくらい。
ネット上でも数多く解説されていますが、古い情報もまぜこぜで、
今の自分の状況と当てはまる記事を探すのって、わりと至難の業。
「あ、これは商店のパターンね」「これは従業員がいる会社パターンね」とか。
なんかもうよくわかんない!となるのも当然。
 まるか
まるか筆者はフリーランスとなって20年以上の間、
多くの改変と戦ってきました 😭
税法の全てを理解する必要はないんです。自分が該当する部分だけ覚えればいいわけで。
限定すると、案外シンプルな仕組みになっています。
この記事では、フリーランスのデザイナー(クリエイター)が
自分に関わるインボス制度の仕組みがわかるよう、例を作って解説しました。
国が設けた特例3つについても解説しますので、該当すればぜひ利用してくださいね。
個人事業主 = フリーランス
適格請求書 = インボイス
課税業者 = 適格請求書発⾏事業者
免税事業者 = 適格請求書発⾏事業者に未登録の人(令和5年10月1日から )
つまりこういうこと|フリーデザイナーのインボイス制度
国「1,000万円未満の人も課税事業者になったら『登録番号』をあげるよ〜」
国「『登録番号』があれば適格請求書が作れるよ〜」
国「適格請求書じゃないとクライアントは困るだろうねぇ〜」
国「仕事の依頼がなくなるかもよ〜」



でも選ぶのはあなたですよ。
いまのところ強制増税ではないです。
この記事は、デザイナーをはじめとしたクリエイターに多いと思われる次の条件で書いています。
- フリーランス(個⼈事業主)
- 売上は1,000万円未満
- これまで免税事業者であった
- クライアントが課税事業者で原則課税方式をとっている
【図解解説】フリーデザイナーから見たインボイスの仕組み
今年に入り、クライアントから登録の有無と登録番号通知のアンケートが届くようになりました。
インボイス制度にあたり準備をされているだけなのでしょうが、ドキドキしてしまう人もいますよね。
登録してしまえば、仕組みはわりと簡単です。
例を出してみます。
デザイナーを中心に、クライアントおよび外注先のイラストレーターさんの皆が、インボイス発行事業者の場合のお金の流れ(実際にはクライアントと外注先は複数であったり他の経費もあったりしますが)。
- デザイナーが案件を受注し制作をする
- イラストレーターにイラストを発注
- 納品後、イラストレーターからインボイスを受け取る
- クライアントに制作物を納品、インボイスを発行
- イラストレーターに報酬と消費税を支払う
- クライアントから料金と消費税を受け取る
- 消費税の差額分を納付する
しくみ-1024x345.png)
しくみ-1024x345.png)
この例ですと、これまでより実質7万円手取りが減ります。痛手ですね。。。
お情けか、3年間は特例が設けられています!次の章で解説します。
利用しない手はないので、ぜひ読んでくださいね。
期間限定『2割特例』使うのがマスト!
これまで免税事業者だった人が、インボイス制度を機に(適格請求書発行事業者に登録して)課税事業者となった場合に『2割特例(正式名は「インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置」といいます。)』が使えます。
次の人には適用されませんので、ご注意ください。
- 令和5年10月1日より前に課税事業者だった人
- 売上が1,000万円を越した人(その年度)
売上税額の2割分を納める『2割特例』
売上げにかかる消費税額から、売上税額の8割を差し引いて、納付税額を計算できるというものです。
つまり、クライアントから貰った(正式には「預かった」)消費税の2割(20%)を納付するということ。
業種に関わらず、売上税額の一律2割です。
2割特例事例-1024x97.png)
2割特例事例-1024x97.png)
2割特例の適⽤にあたっては事前の届出の必要はなく、消費税の確定申告書に2割特例の適⽤を受ける旨を付記すれば適⽤を受けることができます。
適用期間は令和8年度の申告まで
令和5年分(10月から12月分)の申告から令和8年分の申告までが適用される期間です。
令和9年以降は、いまのところ特例はないようです。原則課税か簡易課税を選びます(課税方式についてはあとの章で解説しています)
2割特例の期間c-1024x375.png)
2割特例の期間c-1024x375.png)
【図解解説】経過措置|80%控除, 50%控除
これは免税事業者と取引があるクライアントが利用できる措置です。
インボイス発行事業者でない人からの課税仕入れであっても、インボイス制度開始から期間限定で、一定の割合を(仕入税額とみなして)控除できるというもの。その限定期間と一定割合は、次の通りです。
| 開始日 | 終了日 | 割合 |
| 令和5年10月1日 | 令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の 80% |
| 令和8年10月1日 | 令和11年9月30日 | 仕入税額相当額の 50% |
インボイス制度開始後、免税事業者との取引でクライアントが不利になる仕組みを図解にしました。
図解の例の場合、クライアントは免税事業者の請求書に従って消費税を支払いますが、支払った10万円は仕入れ控除の対象になりません。
実際には他にも仕入れ(発注)をしていますから、控除できなかった10万円がまるまま納税額になるわけではありませんが、理論上は図の通り。なので2重に消費税を払う形になりますね。
取引-免税事業者-1024x309.png)
取引-免税事業者-1024x309.png)
そうなると、クライアントは損をするわけですから、免税事業者と取引したくないと思うかもしれません。
そうなっては免税事業者(多くはフリーランス)が困るので、クライアント側に対し、しばらくは一定割合の額を控除してもいいよというのが、インボイス制度の経過措置です。
経過措置-2-1024x296.png)
経過措置-2-1024x296.png)
少額特例
『少額特例』の対象は、1取引の⾦額が1万円未満の案件です。
該当するクリエイターは稀かもしれません。
注意 1単価ではなく、1取引につき1万円未満です。
少額特例とは ⼀定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置のこと
内容: クライアントはインボイスがなくても、1万円未満の仕⼊に関して仕⼊税額控除ができる
期間: 2029年11⽉30⽇まで
課税⽅式|フリーランスの選択肢
課税事業者は、2割特例の期間が終わったあと(令和8年9月30日以降)の課税方式を選ぶことができます。
原則課税方式が向いている⼈と、簡易課税方式が向いている⼈とそれぞれ。
原則課税方式は、消費税計算が複雑なので、みなし仕入れ率を50%に固定する簡易課税方式の方が楽です。
ただし!グラフィックデザイナーやディレクターは、印刷代や外注費が50%を超えることがあります。
その場合は原則課税方式にしてください。
筆者もまだ検討中です。
2割特例の期間内にどちらにするか決断したいと思います。
原則課税⽅式(⼀般課税制度)
前々年の課税売上⾼が5,000万円を超えた場合は、有無をいわせず原則課税方式。
収支の差額をぴっちり算出します。
貰った(預かった)消費税額から、仕⼊や外注先に⽀払った消費税額を差し引いた⾦額を納税します。
納税額-3.png)
納税額-3.png)
売上にかかる消費税よりも仕⼊や外注にかかった消費税が多い場合は、マイナスになった差額分の消費税が還付されます。
還付額-1.png)
還付額-1.png)
簡易課税⽅式(簡易課税制度)
売上が5,000万円未満の⼩規模事業者向けに設けられている制度で、簡単に計算ができる⽅法。
業種に応じて売上にかかる消費税の⼀定割合をみなし仕入率として控除ができます。
フリーランスの場合は、第5種事業(サービス業)みなし仕⼊率50%に該当
簡易課税-1.png)
簡易課税-1.png)
【まとめ】
フリーランスのデザイナーから見たインボイス制度の仕組みを解説してきました。
- 適格請求書発⾏事業者(課税事業者)は(適格請求書)インボイスが発行できる
- 『2割特例』は、売上税額の一律2割を納付する
- 『経過措置』はクライアント側のもの
- 『少額特例』が適用できる人は稀
- 2割特例期間の終了後は課税方式を選ぶことができる



理解できてスッキリしたら、
デザイン業務にも集中できますね!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
良かった点や気になった点、わからない点などがありましたら、改善につなげますのでコメントをいただけますと嬉しいです。
情報元となったサイト:国税庁