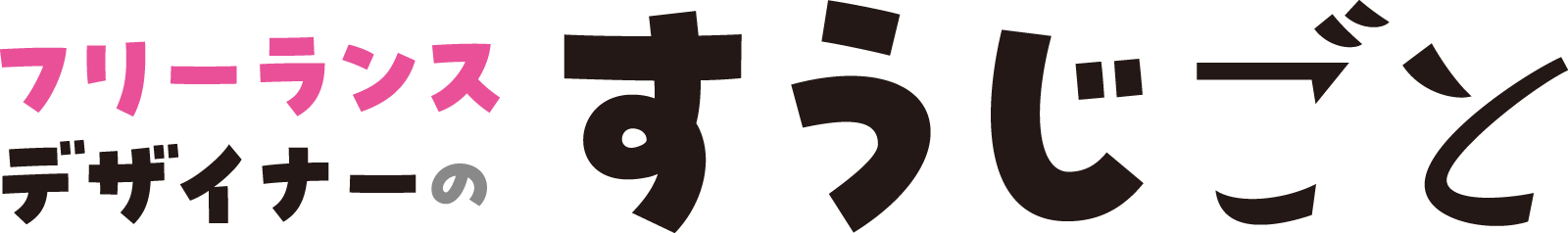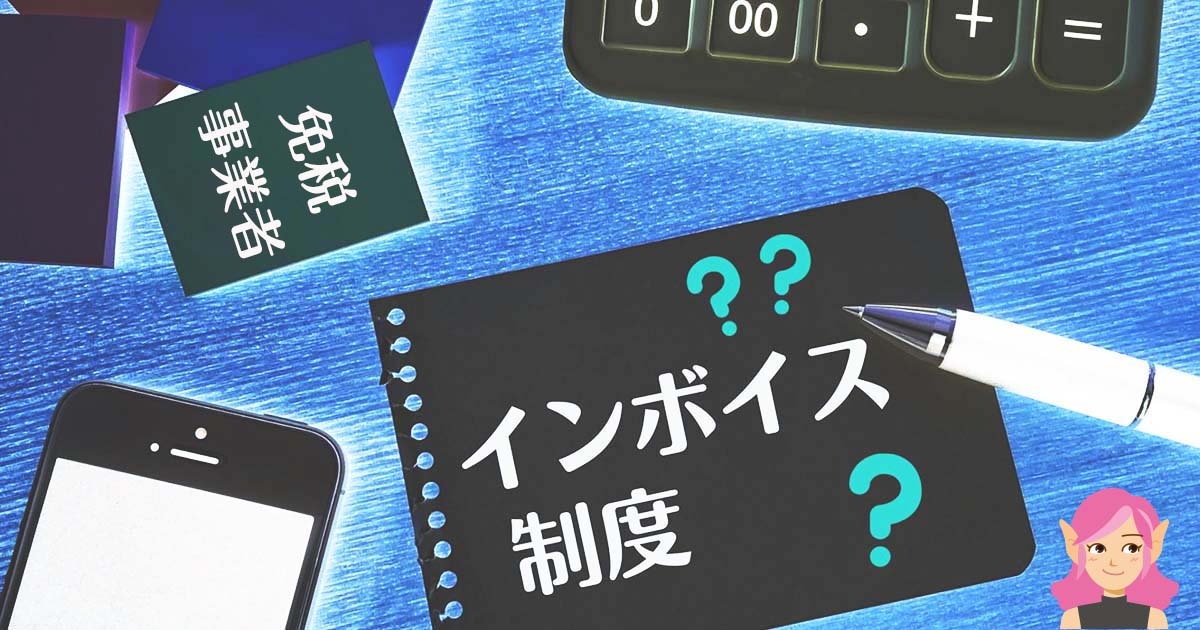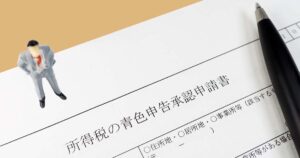反対運動をよそに、あと2ヶ月ほどでインボイス制度が施行されますね(令和5年10⽉1⽇施行)。
『インボイス』とカタカナでライトに表現してますが、要は『増税』なわけで。
企業の肩書きも捨てて、細腕一本でがんばってるフリーランスになんという仕打ちでしょう!
「免税事業者(インボイスに未対応)のままで大丈夫なのかな・・・」
この疑問に、何度も法改正を乗り越えてきたフリーランスの筆者が応えます!
あなたはどこにあてはまる?該当をYES・NOチェック!
- 自分は現在(〜令和5年9月)免税事業者である
YES 質問2へ
NO このままの計算方法です - インボイスを機に課税事業者になった
YES 『2割特例』を使えます
NO 質問3へ - クライアントが免税事業者である
YES 影響はないでしょう
NO 質問4へ - クライアントが課税売上高1億円以下で、
1取引の⾦額が1万円未満の案件のみ受注している
YES 少額特例により影響はないでしょう(令和11年11⽉30⽇まで)
NO 質問5へ - クライアントが課税売上高5,000万円以下で簡易課税方式をとっている
YES インボイス制度施行後も問題ないでしょう
NO クライアントに影響します。何らかのペナルティの可能性があります
ぶっちゃけ!免税事業者のフリーランスは高リスク
クリエイターなのに事業主として雑務に追われる。
調べて、問い合わせて、やっとわかるようになったら法改正。
再び調べて、問い合わせて、対応して・・・
消費税しかり。
「フリーランスへの救済措置があるよね?」
と聞かれることもあるのですが、いいえ…
いまのところ、フリーランスの免税事業者を直接に救済するものは無いんです。
当面『2割特例』と『経過措置80%』がありますが、これらと混乱しているようです。
- 2割特例は、インボイス発行事業者として登録した課税事業者のみに適用。
- 経過措置は、登録していない免税事業者と取引のある依頼主側(クライアント)に適用。
筆者は、免税事業者のままでいることの利点はほぼないという考えです。
なのに免税事業者のままでいたい理由は何か、次の章で具体的に挙げてみます。
それでもインボイス制度に応じたくない⼈の理由
「インボイス制度が始まるのはわかった。それでも免税事業者のままでいたい」
ほんと。せっかく慣れた会計業務、変わるのいやですよね。
具体的な理由について周囲の声を整理してみると、次の5つに集約できました。
- 消費税が複雑すぎる!
- 消費税分の収入が減るのは痛い!
- 確定申告もパニックなのに消費税申告までムリ!
- そもそも適格請求書が何なのかいまいちわからない!
- フリーランスに救済措置ができるかもしれないと期待してる!
なのに国は2ヶ月後にはインボイス制度をスタートするという。
では次に、この先も免税事業者のままでいるメリットとデメリットについて見てみましょう。
免税事業者のままでいる2大メリット
- 消費税相当額を収入にできる!
- 複雑な消費税計算をしなくて済む!
収入は多い方がいいですし、なにより面倒な会計業務は少ない方がいいですよね。
日常の帳簿付けも、消費税の申告も、納付もなくて済むならそれがいい。
どんな人なら叶うのか。
次の人は免税事業者のままでもクライアントへの影響は少ないです。見てみましょう。
そもそも免税事業者のままでもいい人
- クライアントが免税事業者の⼈
- クライアントが課税事業者で簡易課税方式をとっている人
- 『少額特例』対象者=1取引の⾦額が1万円未満の案件しかない⼈(条件あり)
自分が免税事業者でも他に影響を与えない人がいます。次の章で説明します。
少額特例とは ⼀定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置のこと
内容:クライアント(課税売上高1億円以下)は、
インボイスがなくても1万円未満の仕⼊に関しては仕⼊税額控除ができる
期間:令和11年11⽉30⽇まで
注意 1単価ではなく、1取引につき1万円未満です。
当てはまるケースは少ないと思われるのですが、主に1万円未満の受注が多いフリーランスは、免税事業者のままでもクライアントに影響を与える可能性が低いということになります。
あともうひとつ!こちらも免税事業者のままでよいでしょう。
- そろそろ引退しようと考えている人
一般企業ならとっくに定年を迎えている御年の先輩がおっしゃっていました。
「それでもいいよと言ってくださるクライアントとのみお付き合いをしますよ」
次はデメリットについて具体的に見ていきましょう。
免税事業者のままでいることのデメリット5つ
- 今後の罰則や課税への対応の可能性による心配
- 売上額を1,000万円未満に抑える必要がある
- インボイスの発⾏ができない
- クライアントに負担をかけるおいめ
- 受注が減る可能性がある
ひとつずつ確認します。
1 今後の罰則や課税への対応の可能性による心配
いずれ消費税申告が義務化されるのではないか?という懸念があります。
申告をしないと罰則が課せられるのではないかという心配も。
もしそう改変されると、課税業者として対応せざるを得なくなります。
しかし仮にそうなるとしても、まだ先の話であると筆者は考えます。
2 売上額1,000万円未満に抑える必要がある
現在は、売上が1,000万円を超えると消費税課税事業者となり、超えた決算期の2年後に適用開始です。
これはインボイス制度の施行後も同じ。
免税事業者でいるためには売上額を1,000万円未満に抑える必要があります。
逆にいうと、課税事業者は1,000万円という基準値を気にせずに売り上げることができるということ。
グラフィックデザイナーの中には、筆者のように印刷も請け負う人もいますので、印刷費を含んだ売上1,000万円はわりと際どい数字です。
(筆者は平成15年度、売上基準額が3,000万円から1,000万円に引き下げられた時に泣きました!)
インボイス制度の開始後、免税事業者が売上1,000万円を越して消費税課税事業者となった場合、残念ですがあとの章にあります『2割特例』を利用できません。
3 インボイスが発行できない
適格請求書発⾏事業者でないということは、登録番号がありません。
よって、インボイス(適格請求書)の条件を満たす請求書は発行できないのです。
4 クライアントに負担をかけるおいめ
受け取った請求書が『適格請求書』でなければ、クライアントは『仕⼊税額控除』を受けられなくなります。
控除が受けられないとは、そのまま多く税金を納めなくてはいけないということ。
自分が払わなかった税金を、クライアントが肩代わりするようなこと。
(次の章で詳しく解説します)
メンタルが強い人は平気かもしれませんが、クライアントに負担をかけることに対し、おいめを感じてしまうかも。
5 受注が減る可能性
クライアントは免税事業者と取引をすることで多少なりとも負担が増えます。
であれば、インボイスを発行できるデザイナーと取引をしたほうがいいとなる可能性はありますよね。
クリエイターは『自分しかできない仕事』を評価してもらってます。
なので、引き続き依頼は来るだろう。
そう思いますが、相手は組織。担当者はよくても企業の方針で受注が減る可能性はあります。
後の章で、予想されるクライアントからの対応を挙げました。
まずは、クライアントの負担とはなにかを解説します。
【図解】⾃分は免税で、負担はクライアントに!
免税事業者のままであれば自分は何もしなくていいのですが、クライアントがどうなるのか気になりますね。(クライアントが年商5,000万円未満で簡易課税の場合を除く)
さきほどの通り、受け取った請求書が『適格請求書』でなければ、クライアントは『仕⼊税額控除』を受けられなくなります。
つまり、次の図の状態です。
実際には源泉徴収などもありますし、消費税も仕入で払う分と売上もらう分があるので、図ほど単純な計算ではありませんが、極論、こういうこと。
取引-2-1024x694.png)
そこで財務省は、免税事業者と取引のある事業者に対し『仕⼊税額控除の経過措置』をもうけました。
この経過措置によって、免税事業者との取引について6年間は⼀定割合の仕⼊税額控除を受けることができるようになっています。
経過措置-2-1024x296.png)
| 仕入税控除割合 | 適用期間 |
|---|---|
| 仕⼊税額相当額の80% | 2023年10⽉1⽇〜2026年9⽉30⽇ |
| 仕⼊税額相当額の50% | 2026年10⽉1⽇〜2029年9⽉30⽇ |
| 控除なし | 2029年10⽉1⽇〜 |
これはクライアント側への措置です。
この経過措置をフリーランス向けであると混乱されている人もいるようです。
確かに、クライアントの負担が緩和されれば、免税事業者との取引に対し急激に策を打ち出されることはなさそうです。
とはいえ経過措置の期間中も、クライアントが免税事業者への支払額の2%〜5%を負担することにはなります。
経過措置についてはこちらの記事を参考にしてください。

免税業者は何かしらのペナルティへの覚悟が必要になるかもしれません。
次の章では、そのペナルティについて考えてみましょう。
インボイス開始後|予想されるクライアントからの対応
免税事業者との取引に対するペナルティ(対策)を予想します。主に次の3つが考えられます。
| 考えられるペナルティ(対策) | その影響 |
|---|---|
| 報酬額を税込にする | 仕⼊税額画自己負担になる |
| 消費税を請求されても⽀払わない | クレームもつけにくい (下請法で保護されています) |
| 取引を辞める | 受注案件の減少する |
インボイス制度反対運動のニュースなどでもよく聞きますね。これらはあくまで予想なのですが、クライアント側もできれば損失を出したくないということを念頭においておかないといけませんね。
クリエイターだから「報酬を増やしてでもあなたに頼みたい」と言われるのがBESTなんですが。
では、心配している課税事業者(インボイス発行事業者に登録)の税負担はいかほどでしょうか。
次の章で解説します。
【解決!】課税業者になっても2割特例がある!
消費税は、売上のそのまま10%を納税するわけではありません。
貰った(預かった)消費税分から、外注や購入で支払った消費税分を引いた額が、消費税の納付額となります。
売上税額(売上10% 預かった消費税) ー 仕⼊税額(仕入10% 預けた消費税) = 消費税の納税額
例:売上1,000,000円 10%100,000円 ー 仕入500,000円 10%50,000円 = 納税額 50,000円
納税額-3.png)
さらに、インボイス制度が始まる令和5年10月1日から4回分の申告は、次の2割特例が使えます。
2割特例
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の条件は次のとおりです。
| 対象者 | インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人 |
| 納付税率 | 業種に関わらず、売上税額の一律2割を納付 |
| 適用期間 | 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間 |
2割特例-2.png)
売上税額(貰った報酬の消費税)の一律2割 = 消費税の納税額
例:売上1,000,000円 売上税額100,000円 2割20,000円 = 納税額 20,000円
【結論】フリーデザイナーが免税事業者でいる利点は少ない
免税事業者のままでいい人は、次の人でしたね。
- クライアントが免税事業者の⼈
- クライアントが課税事業者で簡易課税方式をとっている人
- 『少額特例』の対象者
これらに当てはまらない人は、インボイス事業者への登録を検討してみてください。
あとで取り消しもできます。
免税事業者を理由に支払い報酬が減ったのでは、むしろ費用対効果はよくないですからね。
課税業者になってもは、当面(令和9年9月30日まで)特例があることを解説しました。
 まるか
まるか当面の消費税計算は簡単。
売上の2%ですね。
免税事業者は費用的な理由以外にも、消費税申告の手間がない利点もあります。
しかし、クライアントと良好な関係を維持したまま、より売上を増やす方に注力する方が生産的です。
これらの理由から結論、フリーデザイナーが免税事業者でいる利点は少ないとしました。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
良かった点や気になった点、わからない点などがありましたら、改善につなげますのでコメントをいただけますと嬉しいです。
情報元: 国税庁〈適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き〉